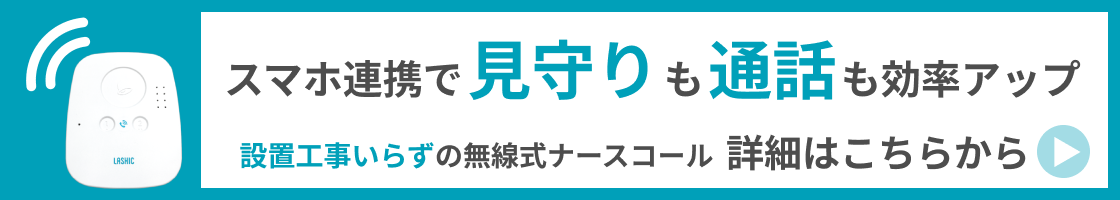作成日:2022/07/17
更新日:2026/02/03

目次
- ・ナースコールには無線式と有線式がある
- ・有線式ナースコールの課題
- ・ナースコールの無線化による5つのメリット
- ・メリット①:導入コストを抑えられる
- ・メリット②:お部屋のレイアウトが自由になる
- ・メリット③:広い範囲でコールできる
- ・メリット④:他のセンサーと連携しやすくなる
- ・メリット⑤:家庭向けに対応した種類のナースコールもある
- ・ナースコースの無線化による2つのデメリット
- ・デメリット①:電池交換や電源との接続が必要となる
- ・デメリット②:電波状況により動作が不安定になる
- ・ナースコールの無線化で広がる可能性
- ・ナースコールの無線化による業務効率化
- ・ナースコールの無線化はフレキシブルな施設運営に役立つ
- ・まとめ
ナースコールは、介護施設において入居者・利用者の命を守る重要な呼出用の機材です。
例えば、ボタン一つで、スタッフへ呼び出しが届くので、この機能は迅速な対応を可能にし、安心・安全な施設運営を支える基盤となっています。
ただし、ナースコールは、一度導入すると10年以上にわたって使用され続ける製品になることも珍しくありません。近年では、施設の構造や介護体制に合わせて、有線型・無線型といったさまざまな型からナースコールを選択できるようになっています。
中でも、ワイヤレスで、配線の自由度が高い無線型は、ベットの移動が頻繁にある施設や新たにナースコールを導入したい施設に適した型として注目されています。ナースコールの使い勝手や呼び出しのしやすさは、職員の業務効率だけでなく、入居者の満足度にも大きな影響を与える要素です。
そのため、新たな導入や入れ替えを検討している施設にとっては、用途や設置環境に合った型を見極め、製品の一覧を比較検討しながら、必要な機能や受信機のタイプなどを十分に確認したうえで選ぶことが重要です。
本コラムでは、ナースコールの無線化に注目し、そのメリット・デメリットについて徹底解説します。施設の呼出機器選びに役立つ情報をまとめていますので、ぜひ導入の参考にしてください。
■特許取得の離床予測を活用!テクノロジーで介護を変える見守りシステム
ナースコールには無線式と有線式がある
ナースコールには、大きく分けて「有線式」と「無線式(ワイヤレス)」の2つの型があります。有線式は、壁面はベッドサイドの接続口とナースコール機をコードでつなぐタイプで、病院や介護施設などで長年利用されてきた製品です。
電池交換の必要がないという利点がありますが、設置場所が限られ、配線工事が必要となるなどの課題もあります。
一方、無線式(ワイヤレス)ナースコールはWi-Fiなどを利用して送信機と受信機が通信するコードレスな商品です。
ボタンを押すだけで呼出信号が送信され、音や光(ランプ、LED)で表示されます。
設置場所に制約が少なく、在宅や家庭、店舗、受付、玄関など、さまざまなシーンに対応できるのが特長です。
有線式ナースコールの課題
有線式ナースコールは、防水性や安定性に優れた仕様のものもありますが、線でつながっているため、ベッドや家具の移動に柔軟に対応しづらいという難点があります。
また、増設や移設のたびに配線工事が必要になるため、導入コストが高くなるケースもあります。介護施設においては、高齢者や患者の状態変化に応じて環境を変える必要があるため、柔軟性のない型は運用に負担をかけることがあります。
ナースコールの無線化による5つのメリット

有線式ナースコールの課題をカバーする方法として、ナースコールの無線化(ワイヤレス)があります。
無線化(ワイヤレス)することにより、以下の5つのメリットがあります。
メリット①:導入コストを抑えられる
無線化のメリットの1つ目は、導入コストが抑えられることです。有線式ナースコールを導入する際は、本体から各部屋を線でつながなくてはならないため、大規模な工事を必要とします。そのため、有線式では高額な導入コストがかかってしまいます。
無線式ナースコールは送信機と受信機を登録すればすぐに使用できるため、工事費を抑えられるのが魅力です。設置もコンセントに差し込むだけで簡単に行え、購入後すぐに運用を開始できます。初期価格を抑えたい施設や家庭向けとして人気の高い商品です。入居者の居室だけではなく、食堂やホールなどにも対応できるようになります。
メリット②:お部屋のレイアウトが自由になる
無線化(ワイヤレス)ナースコールはコードレスなので、ベッドの位置や家具の配置に影響を受けません。
居室やトイレ、ドア近くなど、必要な場所に自由に送信機を設置でき、利用者のニーズに応じたレイアウトに調整可能です。
高齢者の生活動線を考慮した空間設計が実現できます。
つまり、利用者や入居者のこだわりや介護方法に適したレイアウトにすることが可能で、パーソナライズされた環境の実現は、満足度の向上にもつながります。
メリット③:広い範囲でコールできる
無線型は、見通し300メートル以上の距離でも通信できる仕様の製品もあり、屋外や複数フロアでも呼び出しが可能です。
音やLED表示でスタッフに警報を伝えるため、万が一の緊急時にも即座に対応できます。
メリット④:他のセンサーと連携しやすくなる
無線式(ワイヤレス)ナースコールはWi-Fiを利用して通信を行うため、良好な通信環境下で利用することとなります。
このような環境下であれば、Wi-Fiを利用した他のセンサーとの連携が可能です。
Wi-Fi接続を活用することで、赤外線センサーや感圧式センサーなどの介護用品と連携しやすくなります。患者や利用者の動きに応じて自動で呼出が行われるモードも設定でき、連絡手段の一元化や事故防止に効果的です。
また、インターホン機能付きで通話や会話ができる製品もあり、看護スタッフと利用者が直接やりとりできる環境も構築可能です。
メリット⑤:家庭向けに対応した種類のナースコールもある
無線式ナースコールは、ワイヤレスでコードレスな仕様のため、自宅や在宅介護にも取り入れやすいのが大きな魅力です。
家庭向けの小型送信機や卓上受信機は、玄関やトイレなど必要な場所に簡単に設置でき、子どもや高齢者の見守りにも活用されています。
価格も手頃で、注文からすぐに使えるセット商品も多く、お客様の生活スタイルに応じた選択が可能です。
■特許取得の離床予測を活用!テクノロジーで介護を変える見守りシステム
ナースコースの無線化による2つのデメリット
ナースコールの無線化は、メリットがある一方で2つのデメリットもあります。
ここでは、デメリットと対策方法について紹介します。
デメリット①:電池交換や電源との接続が必要となる
無線化(ワイヤレス)ナースコールは、充電式や電池式の送信機・受信機が多く、定期的な接続確認や電池交換が必要です。
注文時には充電時間や電池寿命などの仕様を必ずご確認ください。
デメリット②:電波状況により動作が不安定になる
無線式(ワイヤレス)ナースコールは、通信機器の設置状況や周辺の干渉によって動作が不安定になる可能性があります。
適切な位置への設置やサポート機器の導入、通信環境の確認が大切です。
対応策としては、無線式の利用範囲に電波をしっかりと届けられるよう、通信環境を整備することです。
通信機器を適切な場所に配置したり、通信を補助する機器を導入したりすることで、電波状況が不安定になるのを防げます。
ナースコールの無線化で広がる可能性

ナースコールの無線化による業務効率化
ナースコールの無線化によって、センサーと連携した「離床予測システム」のような新たな機能の導入も可能になります。看護業務の負担を減らし、夜間の見守り強化や履歴管理の精度向上など、医療と介護現場のICT化を促進します。操作が簡単で使える環境を整えることで、スタッフの離職防止にもつながります。
弊社では、さらに一歩進んだ可能性として「離床予測」システムを開発しました。従来、赤外センサーや感圧式センサーなどは、利用者さまの動きを感知してから介護スタッフにお知らせしていました。しかし、それでは介護スタッフが急いで駆けつけても間に合わないケースがあります。
そこで、「離床予測」の出番です。各種センサーとAIによって離床する前に予測をお知らせすることで、従来のシステムでは間に合わなかったケースも余裕をもって対応できます。
利用者さま・入居者さまの転倒やケガのリスクをさらに減らせるでしょう。また、介護スタッフにとっても「離床予測」システムがあることで、「センサーが反応したら、すぐに駆けつけなければならない」というプレッシャーの軽減にも役立ちます。
このようにナースコールの無線化は、さまざまな機能拡張と可能性を広げる点で非常に有用です。さらに、近年では、スマートフォンと連動して呼出の通知を受信できるサービスも登場しており、職員が外出中や他のフロアにいてもリアルタイムに呼び出しを確認できます。
音やチャイム、バイブレーションによる警報機能付きの通知で、見落としを防ぎ、緊急時の迅速な対応を可能にします。スマートフォンとの連動機能を活用することで、従来の卓上受信機に加えたモバイル対応の強化が実現し、より柔軟で効率的なナースコール運用が可能になっています。
ナースコールの無線化はフレキシブルな施設運営に役立つ
無線式(ワイヤレス)ナースコールの導入により、呼出のタイミングや場所を問わず迅速な対応が可能になります。
高齢者や患者の安全を守ると同時に、施設側の方針やニーズに柔軟に応じた設定やカスタマイズも行いやすくなります。
ワイヤレスでコードレスな仕様は、トイレや居室、玄関などにも簡単に設置でき、家庭向けや在宅介護にも最適です。
また、介護ロボットやIoT製品と連携できる通信環境の整備にもつながり、今後の家庭や在宅ケアへの応用も進んでいくでしょう。厚生労働省では、介護職員の人手不足や被介護者の増加に対応するため、介護ロボットの開発と普及を積極的に推進しています。
参考:厚生労働省「介護ロボットの開発・普及の促進」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000209634.html
このような背景からも、無線型のナースコールの導入は、今後の施設運営においてますます重要性を増していくといえるでしょう。また、介護ロボットやIoT製品と連携できる通信環境の整備にもつながり、今後の在宅ケアや家庭への応用も進んでいくでしょう。
まとめ
ナースコールの無線化は、施設・家庭・在宅などあらゆる環境での使用に適した選択肢です。
ボタン一つで呼出できる機能は、高齢者や患者の安心につながり、受信機での音や光による表示も明確です。
タイプやサイズ、価格の異なる多様な製品の中から、お客様のニーズに応じた商品を一覧で比較し、詳細ページや仕様ガイドを参考にして最適なモデルを選択することが大切です。
呼び出し回数の履歴確認、インターホンによる会話、LEDやランプの表示、送信と受信の自動登録、防水・防塵設計など、セットに含まれる器や送信機の機能をしっかりと比較しながら、信頼できる会社の製品を購入しましょう。
採用情報や個人情報保護方針のチェックも忘れずに行い、長期間安心して使用できるナースコールを導入してください。